社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
平成25年(2013年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、「番号制度」)が導入されています。
番号制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされています。
番号制度が導入されると
○申請者が窓口で提出する添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。
○より正確な所得が把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
○社会保障・税・災害対策に関する分野で事務の効率化が図られます。
個人番号(マイナンバー)について
平成27年10月にマイナンバーが通知されます。
○平成27年10月から、住民票を有する市民の皆さん一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が付番され、通知カードが郵送されています。
令和2年5月25日以降にマイナンバーを新規で取得される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
平成28年1月からマイナンバーを利用します。
○平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まっています。
○社会保障、税、災害対策に関する分野で、法律や自治体の条例で定められた行政手続において利用されます。
国や地方公共団体などで利用します。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなりますので、年金・雇用保険・医療保険の手続、児童手当その他福祉の給付、確定申告など税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
○個人番号(マイナンバー)が必要となる手続き一覧について(市ホームページ)
個人番号カードについて
個人番号カードの交付を希望される方は、通知カードに同封された申請書により、通知カードと引き換えに「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが掲載されており、本人確認のための身分証明書として利用できます。
なお、住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カードを取得した場合は、その時点で住民基本台帳カードは廃止・回収することとなります。
○マイナンバーカードについて(市ホームページ)
○マイナンバーカードに関するパンフレット・チラシなど(内閣府ホームページ)
差出有効期限切れのマイナンバーカード交付申請用封筒の取扱いについて
「通知カード」および「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしているマイナンバーカード交付申請用封筒の差出有効期限が 平成29年10月4日になっている場合でも、切手を貼らずにそのまま使用することができます。
交付申請用封筒がお手元にない場合、封筒の素材をダウンロードすることもできます。
※縦型の定型封筒に宛名用紙を貼り付ける方法と封筒を組み立てる方法があります。
○申請書送付用封筒の作成について(PDF形式:156KB)
○「社会保障・税番号制度」(内閣官房ホームページ)
個人情報の保護について
マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続きで国や地方公共団体、勤務先、年金・医療保険者などに提供するものであり、他人にマイナンバーを提供することや他人のマイナンバーを不正に入手することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、個人のプライバシー等に与える影響を、予測・評価し、その影響を軽減するための措置を実施します。(特定個人情報保護評価)
内容が確定した特定個人情報保護評価書については、随時公表していきます。
○特定個人情報保護評価について(個人情報保護委員会ホームページ)
国の取組みについて
内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページおよび政府広報オンライン
番号制度の詳細および最新情報につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」および政府広報オンラインをご覧ください。
○「社会保障・税番号制度」(内閣官房ホームページ)
○マイナンバー特集ページ(政府広報オンライン)
コールセンターのご案内
内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。
電話番号 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)(無料)
受付時間 平 日9時30分~20時00分(年末年始を除く。)
土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く。)
※おかけ間違いのないよう、くれぐれもご注意ください。
※音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報の番号を選択してください。
≪参考:音声ガイダンスで案内される番号は次のとおりです≫
1: 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
2: マイナンバーカードの紛失・盗難について
3: マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4: マイナポータルに関するお問い合わせ
5: マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3627-0952
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
0570-010076
第2弾マイナポイント事業について
2023年9月30日をもちまして、第2弾マイナポイントの申込みは受付を終了しました。
国は、令和2年度から、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、マイナポイント事業を実施しています。令和4年1月1日からマイナポイント事業第2弾が始まり、下記の方を対象にポイントが付与されます。
| 対象者 | 付与ポイント | |
| ① | マイナンバーカードを取得された 方のうち、マイナポイント第1弾に 申し込んでいない方(マイナンバ ーカードをこれから取得される方も含みます。) |
最大5,000円相当のポイント |
| ② | マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方 | 7,500円相当のポイント |
| ③ | 公金受取口座の登録を行った方 | 7,500円相当のポイント |
- 対象となるマイナンバーカード 令和4年12月末までに交付の申請をされた方
- 第2弾マイナポイントの申込期限 令和5年2月末まで
①は、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの登録・申込を行い、キャッシュレス決済をご利用(チャージまたはお買い物)することで、ご利用金額の25%分(1人当たり20,000円のご利用で、最大5,000円分)がポイントとして還元される制度です。
令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
制度の詳しい内容、マイナポイントについての最新の情報は、「マイナポイント事業について(総務省)(外部リンク)」をご確認ください。
事業者の皆さんへ
○事業者の皆さんは、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などの際、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載します。
○個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理の際は、安全管理措置などが義務付けられます。
○国の特定個人保護委員会が、マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインを作成していますので、下記リンク先からご確認ください。
○個人情報保護委員会ホームページ
○所得税など国税のマイナンバーに関する情報は、国税庁ホームページで公開されています。下記リンク先からご確認ください。
○国税庁ホームページ
お問い合わせ
○マイナンバー制度全般について
総務課
電話:(087)894-1111
FAX:(087)894-4440
E‐mail:somu@city.sanuki.lg.jp
○個人番号の通知および個人番号カードに関することは
市民課
電話:(087)894-9218
FAX:(087)894-3000
E‐mail:shimin@city.sanuki.lg.jp
- 電話:(087)894-1111
- ファックス:(087)894-4440
- メールアドレス:somu@city.sanuki.lg.jp







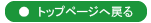


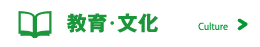

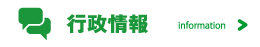
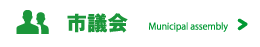
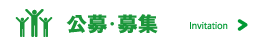








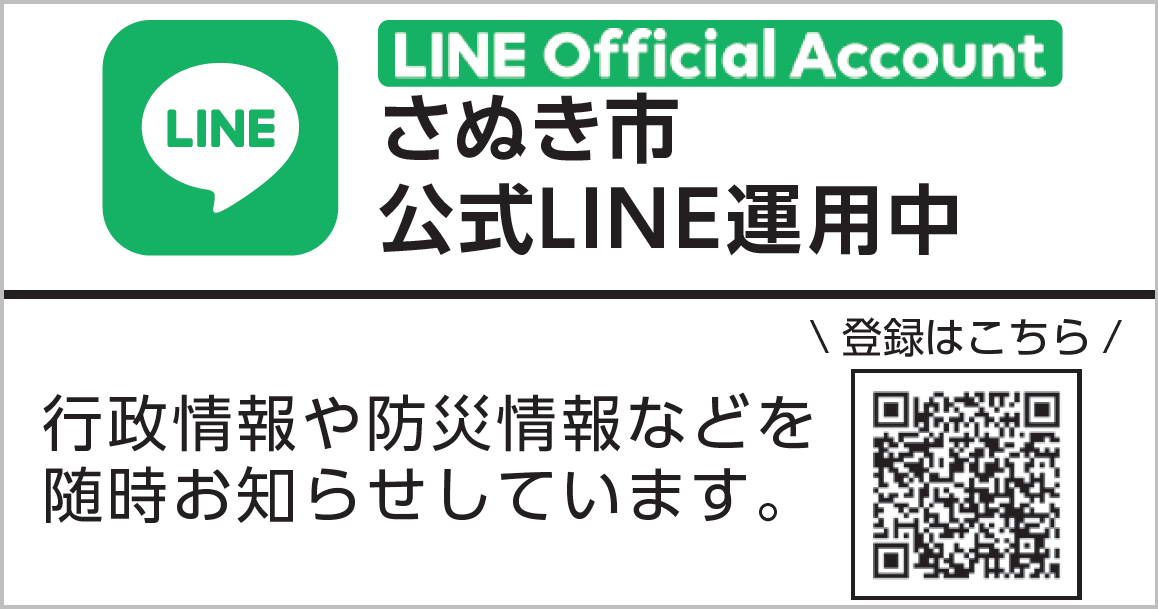


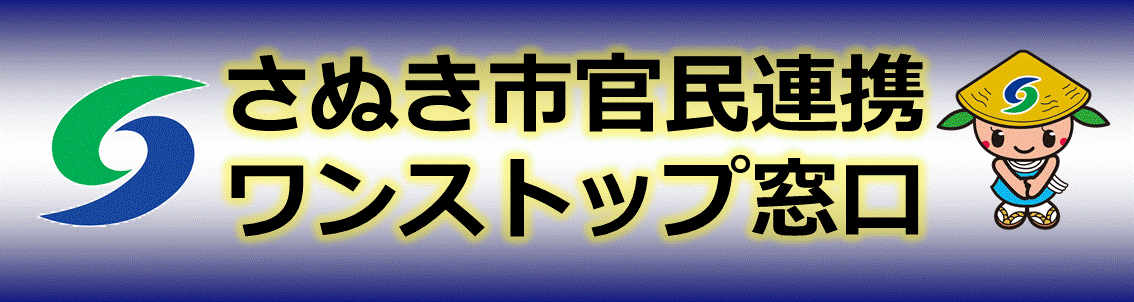





 代表電話:087-894-1111(総務課)
代表電話:087-894-1111(総務課) FAX:087-894-4440
FAX:087-894-4440
