第1 国の動向
わが国の経済は、東日本大震災と原発事故を契機とした深刻なエネルギー制約、世界的な景気の減速、超高齢化社会の到来といった様々な困難に直面している。 また他方では、毎年度巨額の赤字国債を発行する状態が恒常化し、長期債務残高が累増を続けており、経済や国民生活に極めて大きな悪影響を及ぼしかねない状況である。
平成25年度予算を含めた当面の財政運営に当たっては、「中期財政フレーム」の遵守、「日本再生戦略」を踏まえた成長と財政健全化の両立、平成26年度からの社会保障・税一体改革による消費税率引上げに伴う行政の効率化・簡素化への取組など、重点的・戦略的な予算に向けて、省庁の枠を超えて大胆な組替えを行うこととしている。
平成25年度概算要求組替え基準では、平成32年までの「日本再生戦略」の実現に向け、「エネルギー・環境」「農林漁業」「健康」の3分野へ予算を重点配分する一方、公共事業費などの1割カット、予算の組替えのための類似施策の重複排除の徹底、義務的経費や社会保障関係費の制度の根幹からの見直しと徹底した効率化の実施、前例踏襲主義の排除など、厳しい基準が示されているところである。
さらに、国政が極めて不安定かつ流動的な状況にあることから、今後の動向を注視し、速やかに対応していく必要がある。
第2 地方財政の現状と課題
地方財政の状況は、長引く景気の低迷により税収が大幅に回復することは期待できず、一方で、少子高齢化等に伴う社会保障関係経費が増加するとともに、臨時財政対策債の発行などに伴い、地方債残高が平成24年度末で200兆円程度となる見込みであり、さらに、今後も東日本大震災からの復興対策に係る多額の災害復旧債や歳入欠かん債の借入が見込まれ、その元利償還が将来の財政を圧迫することが懸念されるなど、極めて深刻な状況である。
一方で、地域主権一括法の成立や補助金等の一括交付金化など、地方分権・地域主権への動きはますます加速している。こうした中、市町村は、住民に最も身近な自治体として、様々な住民ニーズに機動的かつ弾力的に対応していく必要がある。そのためには、国と地方との信頼に基づき、これまで以上に財政健全化や行財政改革の取組を進め、将来にわたって持続可能な財政基盤を構築するとともに、活力ある地域社会を作るため、自主性・自立性を高めた行財政運営への転換が急務となっている。
第3 本市財政の現状と見通し
本市の財政は、平成20年3月に策定した財政健全化策に沿った種々の取組などによって、市債残高がピーク時よりも66億円(△20.5%、23年度末)減り、財政健全化法に規定する健全化判断比率である実質公債費比率が、19.1%(前年度比1.7%減)、経常収支比率も86.3%(前年度比2.1%減)となるなど、健全化に向けた一定の成果が表れつつあるものの、依然として高い水準にあることに変わりはなく、財政構造の硬直化は未だ改善されていない。
今後の財政の見通しとしては、歳入面では、合併算定替による普通交付税の特例措置が平成25年度から5年間で段階的に縮小されることにより、一般財源の大幅な減少が予測され、歳出面では、CATVの光化事業や学校再編整備、防災・減災対策等に伴う公債費負担の増大に加えて、少子高齢化の進行に伴う社会保障関係経費の増加、老朽化が進む施設の維持補修費の増嵩なども想定されることから、財政状況の悪化がより現実的な問題として迫ってきている。
現在策定中の次期財政健全化策(平成25年度~平成29年度)における収支見込みでは、この5年間の交付税減少額の累計は約60億円となり、計画期間中の財源不足額は約15億円と試算している。さらに、特例措置が終了する平成30年度以降は、毎年24億円の減収となる見込みであり、歳出規模の抑制が喫緊の課題となっている。
また、東日本大震災による事業見直し等への配慮から合併特例債の発行期限は5年間延長されたものの、その終了を見越して平成23年度から24年度にかけて集中投資したことにより市債発行額が一時的に増嵩したことから、今後の投資的経費等の事業選択は、さらに慎重を期する必要があり、義務的経費も含め、経常経費全般の縮減に向けた抜本的な取組が急務となっている。
そうした状況下にあっても、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、将来にわたって行政サービスを安定的に継続していくことが重要であり、メリハリをつけた施策の選択と集中、必要なサービスのより効率的な実施及び歳入確保への不断の努力を基本として、健全な財政運営を推進していかなければならない。
第4 予算編成方針
<1>基本方針
市民一人ひとりが、このさぬき市に住んで良かったと実感できる「安全・安心・快適に暮らせるまちづくり」、「人の心豊かなまちづくり」、「活力があり、人が交流するまちづくり」、そして「市民が主体的に活動するまちづくり」を推し進めることを目標として、平成25年度予算を編成する。
特に重点的に取り組む項目として、次の7つを掲げる。
(1)地域防災計画に基づく、洪水、地震対策の強化など、災害に強いまちづくりの推進
(2)学校再編を含めた教育施設の整備をはじめとする教育と文化の振興
(3)活力ある産業基盤づくりと若年層世代の定住環境づくりを進める取組
(4)コミュニティの活性化と市民が主体的に取り組むまちづくり施策の拡充
(5)新市民病院との連携による保健、医療、福祉の充実
(6)土地開発公社の債務削減や自主財源確保対策の強化など、財政健全化策の推進
(7)優れた歴史遺産や自然環境を活用した、人が交流するまちづくりの推進
編成に当たっては、「さぬき市総合計画後期基本計画」に定めた基本施策や具体的取組事項を中心として、現在の市民ニーズを反映した行政課題への対応を図るとともに、すべての事務・事業を精査し予算を立案すること。
その際、「選択と集中」によって、施策・事業の重点化による優先的課題解決といった点にも十分留意すること。同時に、今後とも厳しい財政状況が続くことを念頭におき、無駄を排除し、徹底した簡素・効率化を図って経費と財源の節減に努めることとする。
予算規模については、国の予算編成の動向等を見極めながら今後の編成過程の中で決定していくが、大幅な財源縮小が想定される将来の姿により近づけるため、現時点における経常的調達可能財源の範囲内において、さらに充当一般財源総額の確実な抑制に努める。市債については、残高を削減する方針に留意しつつも、合併特例債発行可能期間と残事業を勘案し、効果的・効率的活用を図るものとする。
以下、予算編成に係る方針として、留意すべき事項を定める。
(1)さぬき市総合計画後期基本計画との整合性
後期基本計画は、平成24年度~26年度の間における市の将来の発展に向けたまちづくりの目標と重点的に推進していくべき戦略及び具体的取組内容等を定めたものである。そうしたことから、盛り込まれた取組内容との整合性に十分留意し、目標の達成につながる予算の内容とすること。
(2)ゼロベースからの再構築
前例踏襲による事業の考え方を改め、すべての事務事業について、ゼロベースから予算の再点検を図り、市民のための効果的な施策が将来にわたって推進できるよう、市民目線、経営感覚など、新たな視点で施策の再構築を行うこと。
(3)コスト意識をもった予算編成
先例にとらわれることなく、以下の事柄に留意して予算を編成する。
・必要性:行政が担う必然性があるか
・効率性:無駄が無く、投入される行政資源に見合う成果が見込めるのか
・有効性:意図する目的・効果を最大化できる手法が選択されているか
・緊急性:上記観点に加え、さらに他事業に先んじて実施するべきものか
(4)財政健全化策の継続・推進
平成20年度策定の財政健全化策に沿った各種の取組をさらに継続、発展させるとともに、現在策定中の次期計画とあわせて、より効果的・効率的な取組の推進を図ること。
(5)後年度負担の考慮
施設の建設、新たなシステム構築などいずれにおいても、以後の管理費や保守委託料など後年度負担が生じることから、それらを十分考慮した上で事業に取り組むこと。
(6)枠配分予算の有効活用
限られた財源の有効活用という枠配分予算のメリットを活かし、部局長の裁量を活かした調整機能を発揮し、変化する行政需要に対して柔軟かつ的確に対応すべく事業の再構築を図ること。
(7)年間総合予算の徹底
年間総合予算として編成し、年度内に必要な経費は、すべて当初予算に盛り込むこと。特に、必要不可欠な経費はまずもって確保するものとし、最初から補正ありきの要求は認めないこと。
(8)特別会計・公営企業会計等
特別会計についても、基本的に一般会計と同じ方針で作成し、独立採算の原則に基づき、安易に一般会計に依存することなく、業務運営の健全化を図ること。公営企業会計についても、基本原則である経済性を発揮し、収益力の向上と事業の効率化による財務体質の強化を目指し、一般会計の負担軽減を図ること。さらに、市が出資する公社、いわゆる第3セクターについても、適切な指導・管理によって健全経営を促進し、市の財政負担が生じないよう努めること。
(9)国・県の予算への対応
現行制度での予算編成を基本とするが、国・県の政策変更や予算編成等の動向を的確に把握したうえで、適切な対応を図ること。
<2>個別方針
1.歳入
自立的な財政運営が求められる中、自主財源の確保が非常に重要となっている。特に、類似団体に比べて財政力が劣る本市にあっては、市税の適正な賦課と徴収の強化はもとより、分担金・負担金及び使用料・手数料の適正化のほか、適切な債権管理に基づく未収金の縮小など可能な限り財源確保に向けた努力を行っていく必要がある。特に未収金対策は、市民間の公平性の確保につながる重要な事項であり、決して疎かにしてはならない。
歳入の見積りにあたっては、社会経済情勢の変動や国・県の施策の動向を見定め、法令、条例等に十分留意し、必要な財源の確保に向けて積極的に取り組むことを念頭において見積りを行うこと。
(1)市税
過去の推移、経済情勢を適正に判断しつつ、税制改正等の動向を見極め、課税客体、課税標準の的確な捕捉に基づき調定見込額を見積もるとともに、収納率向上が使命であることを十分認識のうえ計上すること。
(2)国・県支出金
制度変更の動向把握に努め、適正な計上を図り、廃止や補助率引下げ等によって年度途中における歳入不足に陥ることがないよう注意すること。
補助事業といえども、事業の実施には一般財源を要することを勘案のうえ、緊急度、事業効果等を十分考慮して、その活用に努めること。
(3)分担金・負担金及び使用料・手数料
受益者負担の原則と住民負担の公平性に配慮し、他市の状況なども把握しながら、積極的に見直しを行うとともに、収入未済額の縮小に向けた取組を強化して収入確保を図ること。
(4)財産収入
資産を適正に管理し、積極的かつ効果的に運用して増収を図ること。特に、所管する資産のうち、行政目的の活用がなされていないものは、遊休資産として処分の方針が定まるものから順次計画的に処分して財源確保に努めるとこと。
(5)市債
将来の公債費負担適正化に向けて、安易に市債に頼る事業計画は厳に慎むなど、それぞれが借入額抑制に取り組むこと。
新規事業については、その適債性・充当率について予算調整室と協議するとともに、既存事業についても充当率を確認して見積もることとするが、前年度に市債充当のなかった継続事業への充当は、要求段階で行わないこと。
合併特例債の活用は、「新市建設計画」に計上されている事業で、市の一体性の速やかな確立、市の均衡ある発展、公共的施設の統合整備等に資する事業が対象であること。
(6)その他の収入
新たな財源の確保に積極的に努めると同時に、零細な収入についてもなおざりにすることなく、細大漏らさず見積もること。
2.歳出
歳出については、最小の経費をもって最大の行政効果が得られるよう工夫を凝らし、決して先例や慣例にとらわれることなく、ゼロベースからの積上げによって予算を見積もること。
以下、性質別の留意事項を定める。
(1)義務的経費・準義務的経費
それぞれ必要額を見積もることとするが、人件費の基礎となる職員数は、さぬき市第2次定員適正化計画に基づくものとし、非常勤嘱託職員についても必要最低限度の人員を前提に算定すること。
扶助費については、過大計上を厳に慎むこと。
一部事務組合負担金及び債務負担行為に基づく元利償還助成金は、必要額を計上することとするが、所管の一部事務組合に対して、本市の厳しい財政状況と予算編成方針の周知徹底を図り、新たな大規模投資の抑制と経常経費の縮減を強く求めるなど、主体的に今後の負担金抑制に努めること。
(2)政策的経費
政策的な重点事業として特別枠で要求できる経費であるが、実施方法及び経費のあり方について、再度有効性・効率性の観点から精査したうえで要求を行うこと。
(3)特別需要経費
臨時的又は数年に一度発生する経費、制度変更等により新たに生じた経費等について、特別枠として要求することができる経費であるが、単にシーリングからの除外を目的とした経費も多く含まれていることから、再度内容を精査し、必要最低限の額で要求を行うこと。
なお、以上2項目に係る事前調査について、査定結果を政策特別経費一覧表により別途通知する予定であるが、決定(想定額)はあくまでも上限額として認めたものであり、決定=予算計上額とはならない点に留意すること。
(4)投資的経費
投資的経費は、予算の性質分析上、臨時的経費に位置づけられる経費であり、緊急性、必要性及び有効性を特に考慮し、重点化を図りながら計画的実施に努めること。継続事業についても積極的に見直し、不要不急な事業は、躊躇無く廃止、凍結を行うこと。
事業費の算定に際しては、規模や単価等を適正に積算し、過去の実績も勘案して過大見積りを避け、積算内容が合理的に説明できる要求額とすること。
要求上限額は、特別経費を除いて、一般財源ベースで24年度当初予算額(配分対象外経費を除く)の97%の範囲内とする。
なお、この経費は枠配分という形ではなく、すべてが査定対象となるので、各施策における事業の優先順位を明確にしておくとともに、要求書の提出に当たっては、位置図、施設概要資料及び改修であれば老朽状況を示す資料等を添付すること。
(5)一般行政経費
必要な事業を効果的、効率的に実施するための予算内容とし、既に目的を達した事業や非効率あるいは効果の低い事業は、廃止・縮小を含めて見直すこと。各経費は後記「節別基準表」に基づき積算するものとする。
枠配分額は、24年度当初予算における一般行政経費充当一般財源から配分対象外経費(臨時的事業、終了事業及び継続の政策的経費等に係るもの)を控除した額の98%とする。
特定財源のみで賄われる事業についても、同様の基準とし、オーバーフローが生じる場合は、必ず義務的経費に充当すること。
使用料・手数料等のうち、前年度に義務的経費に充当していた財源を予算要求段階で一般行政経費に充当替えすることは認めない。
(6)特別会計
経営的観点に立った事務事業の効率化と収入確保に努め、業務運営の健全化を図って、一般会計からの繰入れを極力抑制すること。
繰出金については、公債費、保険給付費等に対する定率負担部分は必要最低額を、これ以外については、投資的経費、一般行政経費相当分とも上記一般会計の要求基準に準じて算定し、算定内容を別途通知する確認表に記すこと。
3.特記事項
(1)新規事業は、既存事業の見直しによる財源捻出を原則とする。立案にあたっては、現状における課題、目的、効果、実施方法及び他の施策との関係等を十分検討のうえ整理し、明確にしておくこと。
(2)国・県の補助事業において、補助が打ち切られるものについては、その必要性を再考したうえ、原則として廃止・縮小、若しくは同等の財源で実施可能な効果的代替事業への移行を図ること。
(3)年度を超える契約を新たにする場合は、「債務負担行為見積書」及び「債務負担行為支出予定額等説明書」の作成及び提出が必要である。後年度負担を生じるため、必ず事前に予算調整室と協議し、安易な設定は行わないこと。
(4)枠配分予算及び投資的経費要求額は、「予算要求事業別集計表」を作成し、要求可能範囲内であることを確認のうえ提出すること。







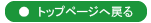


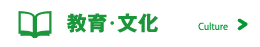

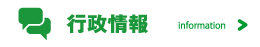
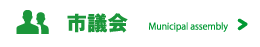
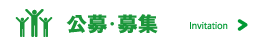








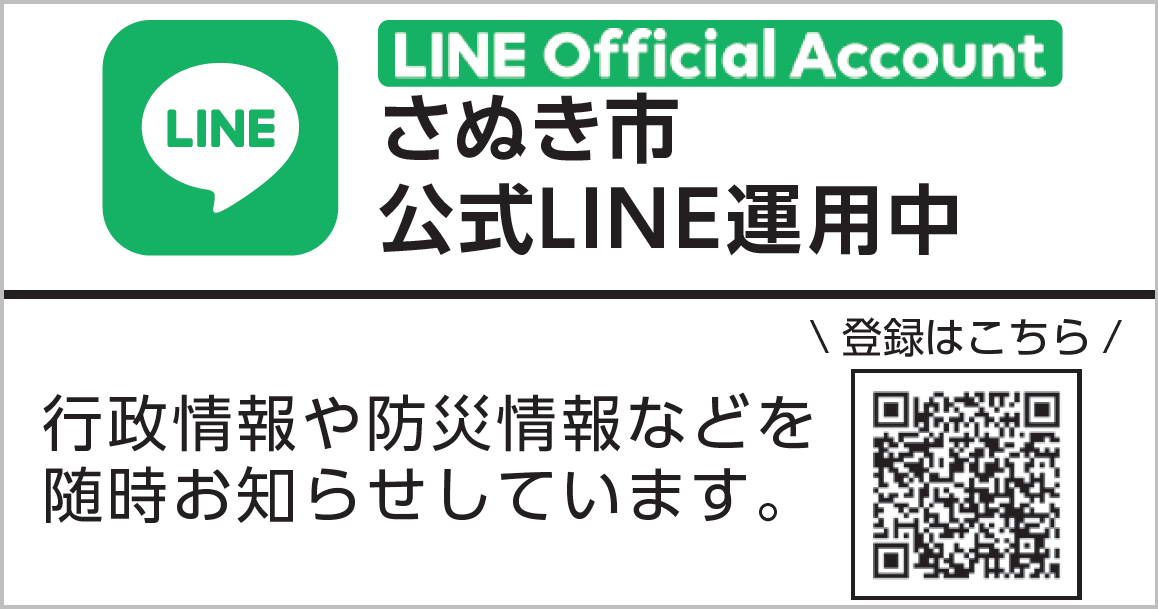


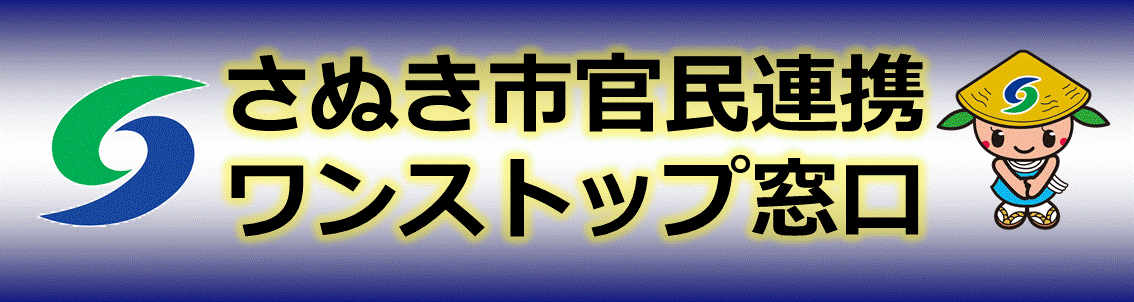





 代表電話:087-894-1111(総務課)
代表電話:087-894-1111(総務課) FAX:087-894-4440
FAX:087-894-4440
