国民年金のしくみ|任意加入制度|年金の届け出は忘れずに|前納制度|保険料の口座振替について|産前産後期間免除制度|一般免除制度|学生納付特例制度|若年者納付猶予制度
国民年金のしくみ
国民年金の加入者は、職業などによって3つの種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
| ・ 第1号被保険者 ・・・ 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の学生、自営業者など
○保険料 【付加保険料】月額400円 |
| ・ 第2号被保険者 ・・・ 会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人
○保険料 |
| ・ 第3号被保険者 ・・・ 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
○保険料 配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、自分で納める必要はありません。 |
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く。)
ただし、申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
○任意加入できる方
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を所有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続をすることができます。
・保険料…第1号被保険者と同額です。
※保険料の納付方法は「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、原則口座振替になります。
年金の届け出は忘れずに
第2号被保険者や第3号被保険者から第1号被保険者になるときは、所在地の市役所またはお近くの年金事務所で手続きをします。
○必要な書類
- 加入する方の年金手帳(基礎年金番号通知書)、またはマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 退職した日付のわかるもの(健康保険の資格喪失証明書、雇用保険離職票など)
前納制度
国民年金の保険料は、2年分、1年分、または半年分まとめて4月(半年分の場合、10月~3月分は10月)に前納することが出来ます。
前納すると、保険料が割引されお得なうえ、毎月保険料を納付する手間が省け、納め忘れの心配もありません。
前納制度を利用する場合は、4月に日本年金機構から送付されてくる納付案内書の中に同封されている前納用納付書にて1年分、または半年分の保険料を4月末までに納付してください。
口座振替の方は、前年度の振替方法に「前納」を選択されている場合、特段の申し出がない限り、毎年、継続して前納で振替を行うこととなります。また、新たに前納を選択される方は、「国民年金保険料口座振替納付変更申込書」を金融機関へ届け出てください。申込書は年金事務所、金融機関、市役所本庁市民課および寒川庁舎国保・健康課にあります。
なお、保険料の前納を口座振替にすると現金納付に比べさらに割引されます。
保険料の口座振替について
国民年金保険料が自分の預金口座から自動的に引き落とされる口座振替は、毎月の保険料の納め忘れが無く、手間も省けます。 手続きは、預金通帳と通帳の届け印、国民年金納付案内書を持って、金融機関または年金事務所で行ってください。
また、通常の口座振替(翌月末引き落とし)は定額保険料ですが、早割制度を利用すると毎月50円が割引となります。
産前産後期間免除制度
第1号被保険者が出産を行った際には、届け出を行うことで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から受付可能です。
○免除期間
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間
○対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
○必要な書類
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 出産予定日のわかる母子健康手帳など(出産予定日で届出をする場合)
一般免除制度
| 経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な方には・・・ 一般免除制度があります!! |
どうしても保険料を納めることが困難な方には、申請をして承認されると保険料が免除される制度があります。
この一般免除制度には、「全額免除」、「4分の1納付」、「半額納付」、「4分の3納付」の4種類があります。
これらの制度をご利用いただく場合は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が、それぞれ一定の基準額以下であることが条件となります。
|
●免除や一部納付の対象となる所得基準
前年所得が、次の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。
| 全額免除 | (扶養親族の数+1)×35万円×32万円 |
| 4分の1納付 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の3納付 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
全額免除や一部納付の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が少なくなります。
10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができますので、余裕ができたらぜひ追納をしましょう。(承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。)
学生納付特例制度
| 収入の少ない学生には・・・ 学生納付特例制度があります!! |
学生本人の前年所得が一定額以下の場合、申請をして承認されれば在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
納付特例期間については、事故や病気で障害が残った場合には障害基礎年金の支給対象となり、また、遺族基礎年金の支給対象となりますが、老齢基礎年金額の計算をする際には反映されないので、より多くの年金を受けるために10年以内に追納しましょう。
※前年度承認されていた方も、今年度の保険料についてはあらためて申請をして承認される必要があります。
納付特例制度(平成28年7月から)
| 学生を除く50歳未満の方は、世帯主の所得を問わず、本人・配偶者のみの所得で判断!! |
50歳未満の方は、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合、申請をして承認されると、承認期間中の保険料の納付が猶予されます。
承認を受けていると、未納とは違い、障害基礎年金等を受けるための納付要件に備えることができ、万が一の時にも安心です。また、納付猶予期間の保険料は10年間以内ならさかのぼって納めることができ、追納すると、将来老齢基礎年金を受ける時に年金額に反映されます。







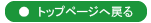


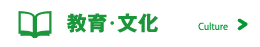

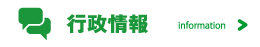
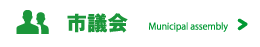
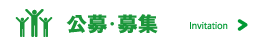








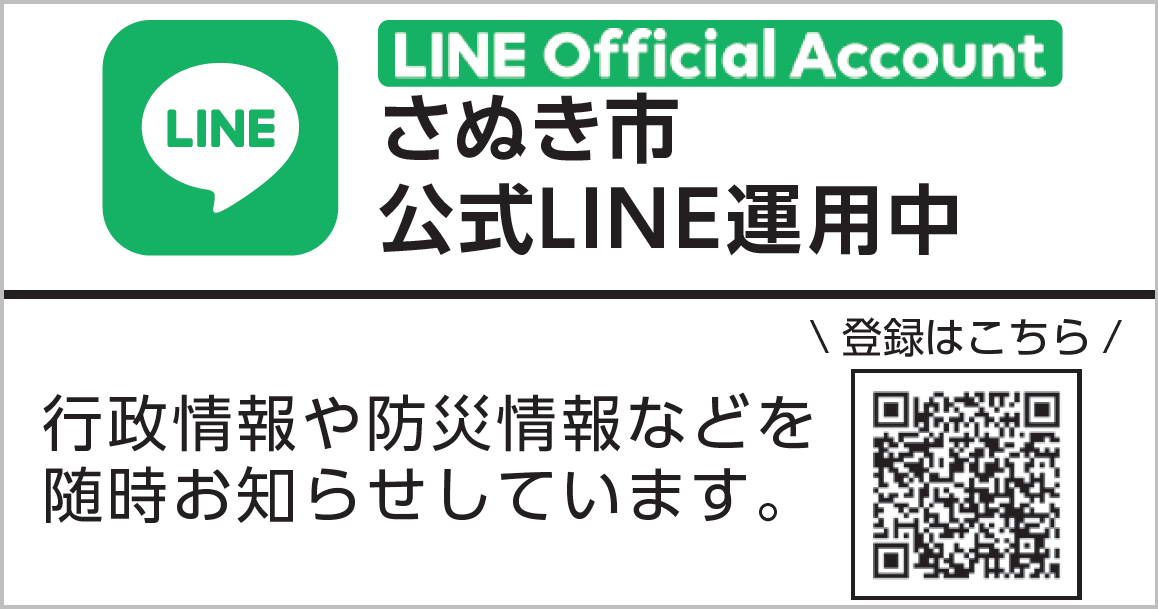


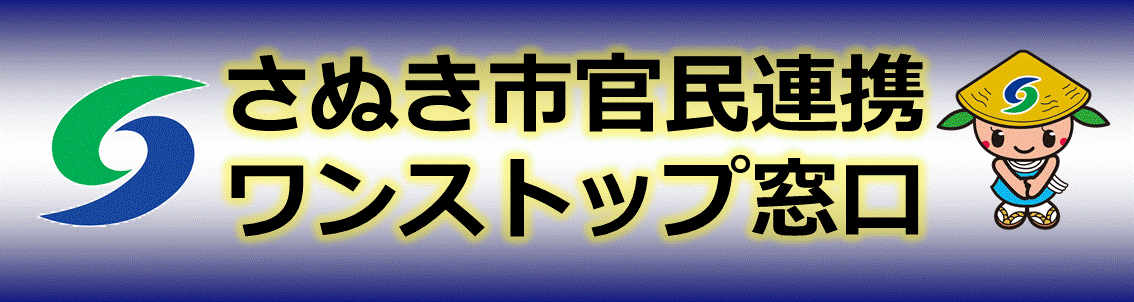





 代表電話:087-894-1111(総務課)
代表電話:087-894-1111(総務課) FAX:087-894-4440
FAX:087-894-4440
